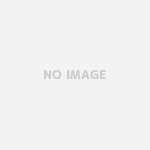最近、会計ソフトにも「クラウド化」の波が押し寄せている。
そこで、このクラウド会計ソフトのメリット・デメリットについて現役の税理士がお話ししたいと思う。
1.クラウド会計ソフトとは
そもそもクラウド会計ソフトの「クラウド」とはどういう意味だろうか?
クラウドとは簡単に言うと、「個別のパソコンにプログラムソフトをインストールしなくても、インターネットを通じて一定のサービスや機能を利用できるシステム」のことを言います。
既存の会計ソフトは個々のパソコンにプログラムやデータを保存していたので、複数のパソコンで会計データの入力などはできませんでした。しかし、クラウド会計ソフトはインターネット上にプログラムやデータを保存するため、インターネット経由で複数のパソコンで利用することが可能です。
2.クラウド会計ソフトのメリット
①複数のパソコンでの利用する場合、利用料金が安い
既存の会計ソフトであっても、すべてのパソコンにプログラムをインストールすれば利用すること自体は可能です。しかし、クラウド会計ソフトの方が1台あたりの料金が安くなる傾向があります。
②銀行預金やクレジットカードとのデータ連携
クラウド会計ソフトは銀行預金やクレジットカードとのデータ連携を強化しています。
そのため、ワンクリックで通帳の入出金を会計データに連動させる機能や、支出先を定型登録することにより自動的に科目が入力される機能などもクラウド会計ソフトの方が優れています。
③法改正への対応
消費税率の変更などの法改正の対応はクラウド会計ソフトの方が優れています。
抜本的な法改正が行われた場合、既存の会計ソフトは通常買い替えの必要が出てきますし、プログラムのバージョンアップを自分で行う手間が発生します。一方、クラウド会計ソフトの場合は通常は自動的にアップデートされます。
3.クラウド会計ソフトのデメリット
①維持費がかかる
通常の会計ソフトの場合、上記のような法改正がなければ当初の購入費用のみで何年でも使用することができます。
しかし、クラウド会計ソフトの場合はアカウント料金という形で月々使用料がかかるため、長期的に維持費がかかることとなります。
②処理速度がインターネット環境に依存する
税理士にとって一番悩ましいポイントはこれです。
通常の会計ソフトはプログラムもデータもパソコン(もしくはサーバー)に保管されているため、処理速度はパソコン自体のスペックにのみ影響されます。
一方でクラウド会計ソフトの場合、インターネット上にプログラムやデータが保管されているため、処理速度はインターネット環境に影響されます。
そのため、多くの仕訳を入力する場合には通常の会計ソフトの方が優れています。
4.まとめ
ゼンはJDL、弥生会計、勘定奉行、MJS、会計王、freeeなど様々な会計ソフトを使用したことがありますが、会計ソフトごとに一長一短で「絶対にこれがいい!」という会計ソフトはありません。
また、基本的にはどの会計ソフトでも仕訳の入力、決算書の作成などできることは同じです。少しだけ操作方法やボタンの配置が違うだけです。
そのため、下記を参考にクラウド会計ソフトにするのか通常の会計ソフトにするのかを判断していただければと思います。
~クラウド会計ソフトが向いている人の条件~
①現金の入出金がほとんどなく、通帳やクレジットカードの取引が多い
→現金の入出金が多い場合は自分自身で仕訳を入力しなければならないので通常の会計ソフトの方が入力が速い。
②インターネットに抵抗がない
→インターネットで物事を調べることや、「チャット」「ブラウザ」などのインターネットの用語に抵抗がある場合はクラウド会計ソフトは向かない。
5.(おまけ)無料サンプル
会計ソフトについては通常「無料サンプル」や「お試し期間」というのがあります。
そのため、カタログやホームページなどと睨めっこするよりかは、一度ソフトを触ってみて判断するのが手っ取り早いです。
クラウド会計ソフトがどんなものなのか知りたい方は、下記のfreeeを一度お試しいただければと思います。
また、クラウドではない通常の会計ソフトを試したい方は下記の弥生会計を無料で試すことができます。