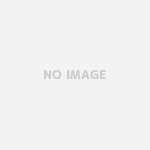初めての開業。
税金のことなんて何もわからないし、めんどくさいし、税理士にお願いしよう!
でも税理士ってどこで探せばいいんだ?どう選べばいいんだ?
そんなことありませんか?
今回は税理士の探し方、選び方について、 税理士自身がお話ししたいと思います。
1.税理士の探し方
税理士を探す方法にはいろいろあります。
- 口コミ、紹介
- 税務署の芳名板
- インターネット
- 仲介業者 などなど
インターネットが普及していなかったころは、
「おたく、どんな税理士さん使ってるの?」 なんて社長同士の口コミから税理士探していたみたいですが、今はあまり誰かの紹介で・・・みたいなのは少なくなりました。
また、とにかく近くで税理士を探すのであれば税務署の芳名板を見るのが一番いいでしょう。
自宅の近くの税務署に行けば税理士の一覧が掲載された立て看板みたいなものがありますので、 そこから選ぶという方法もあります。
ただし、ほとんど事務所にいないような税理士や、高額の報酬を請求する事務所もありますので、実際に良い税理士を探すとなると複数の事務所に連絡する必要があり、面倒です。
また、最近はほとんどの税理士がホームページを公開しているので、ホームページからどんな税理士なのかをだいたい把握してから、見積もりを取って比較してもよいかもしれません。
しかし、何件もの税理士から見積もりを取るのも面倒です。
ゼンとしては仲介業者を利用する方法が一番楽ではないかと思っています。
ある程度の条件を仲介業者の方に伝えれば、その条件に合った税理士を紹介してもらえます。
ただし、仲介業者はすべての税理士事務所を紹介するわけではありません。
あらかじめ税理士事務所と仲介業者で仲介の契約がされているところに限ります。
また、仲介業者を利用した場合、税理士報酬は少し高くなる可能性があります。
なぜなら、税理士事務所は仲介会社に紹介料を支払うからです。
お客様自身は無料で税理士を紹介してもらえますが、税理士は紹介会社に紹介料を払わなければなりません。
すると、税理士報酬に紹介料が上乗せされる可能性があるのです。
2.税理士の選び方
税理士の選び方としては
- 知識
- 事務所規模
- 金額
- 人間性
いろんな意見があるかと思いますが、 税理士の私自身がお勧めする選び方をお話しします。
まず、税理士としての知識がなければ仕事を任せられません。
税金のこともそうですし、最近では保険、補助金、経営マネジメントなどの知識も税理士に求められるようになりました。
ただし、実際に顧問契約した途端、若くて頼りない職員が来るだけで、 税理士が全く顔を見せに来なくなった、なんてことがあります。
そのため、事務所規模にも注意が必要です。
大きい事務所ほど、職員のうち税理士資格を持たない人数の割合が大きくなります。 事務所内に所属する税理士数は多いので、知識面では安心のはずなのですが、実は無資格の担当者が決算書、申告書を作成し、税理士は判子を押すだけ、なんてこともあります。
また、小さな事務所であればお客様の数も多くないため、 所長税理士自身がお客様のもとに訪問することが多いようです。
もし、担当が不安なようであれば、見積もりの段階でどんな人が担当になるのか聞いておいた方が良いと思います。
そして、やはり気にされるのは金額でしょう。
そもそも税理士報酬って月々どれくらいが普通なのかはあまり知られていません。
そのため、必ず複数の税理士から見積書を出してもらうようにしましょう。
では、知識があるかはすぐにはわからないし、 事務所規模も金額もほとんど変わらない税理士が二人いたら、どっちを選べばいいのでしょうか?
そこで最後には人間性です。
人間ですから好きなタイプ、苦手なタイプはわかれると思います。
やはり長く付き合っていくなら、自分と相性のいい税理士にお願いしたいと思います。
ただし、上記で述べたように自分が信頼した人以外の人が担当になる可能性もあるので、 それは事前にご確認ください。
3.(おまけ)税理士の報酬について
お客様に見積書を出すととても驚かれることがあります。
「こんなに安くていいんですか?先生?」
たしかに売上規模は多かったのですが、 月々の取引数は少なく、さらにしっかりと自社で会計データを入力されていたため、 税理士としては入力内容のチェックと経営アドバイスくらいしかやることがありません。
そのため、報酬は月3万円、決算料18万円でお見積りさせていただきました。
しかし前任の税理士の方は月8万円、決算料40万円だったそうです。
その金額の理由としては、昔の報酬をずっと変更しなかったからです。
昔、税理士には報酬規程がありました。
今は各税理士が自由に報酬金額を設定できますが、昔は報酬金額の最高金額が決められていました。
さらにその報酬規程は売上規模のみで報酬を決定していたのです。
そのため、どんなに税理士に負担がなくても、売り上げが多ければ報酬も高くなるという仕組みだったのです。
今もご年配の税理士の方にはこういった報酬規程のままの方もいるようです。
じゃあ、知識があるかはすぐにはわからないし、 事務所規模も金額もほとんど変わらない税理士が二人いたら、どっちを選べばいいのでしょうか? それは最後には人間性です。 人間ですから好きなタイプ、苦手なタイプはわかれると思います。 やはり長く付き合っていくなら、自分と相性のいい税理士にお願いしたいと思います。 ただし、上記で述べたように自分が信頼した人以外の人が担当になる可能性もあるので、 それは事前にご確認ください。 自分の主観で述べていますので、あくまでご参考に・・・・ ちなみに、試験に合格した税理士と、試験を免除された税理士と、税務署のOBの税理士の3種がいるというお話は割愛しました。 私が試験の一部を免除された税理士だというのも一つの理由ですが、 実際税理士として仕事をしていけば必要な知識は備わるものです。 たしかに試験に合格した方々は、すごいと思いますが、実務と試験は別物です。 私自身、試験にすべて合格して税理士になるのが40歳になるよりも 試験は免除してでも、20代のうちに税理士になって実務を経験したほうが良い税理士になれると思っています。