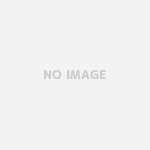相続税のご相談がここ最近多くなっています。
特に多いご相談が今回お話しする「一次相続が未分割であった場合」です。
例えば、Bさんが亡くなられたときに、 Bさんより先に亡くなっていた Bさんの父親Aさんの相続財産の分割が終わっていないといった場合です。
また、少し違ったパターンとしてはCさんが亡くなられて、遺産分割協議が完了する前に 配偶者のDさんが亡くなってしまった場合もあります。
つまり、後に亡くなられた方(「二次相続」といいます。)の相続財産に先に亡くなられた方(「一次相続」)のどの財産が含まれるか、まだ未定の状態という場合、 どのように計算すべきかという問題です。
今回は上記のような場合の手続きについてお話ししましょう。
1.とにかく一時相続を速やかに行う
先に亡くなった方の相続の手続きが終わらなければ、二次相続の手続きが進みません。
一時相続においてどの財産債務を相続するのかが決まってないのですから二次相続もまとめようがないのです。
ただし、一時相続発生からかなり期間があいていた場合、一時相続ををまとめるのがとても困難になります。なぜならば相続人が亡くなっていることが多いからです。
相続人が亡くなっていた場合には、その相続人の相続人(通常配偶者や子)が一時相続の話し合いに関与することとなりますので、相続人の数が増加します。
さらに相続人の数が増加すれば、顔も知らない親族と相続の手続きを進めることとなりますので話し合いが難しくなります。
多いケースは祖父が数十年前に亡くなったが面倒だったので遺産分割手続きを行っておらず、不動産の所有者も未だ祖父名義で登記されているような場合です。
こういった場合、祖父の相続人を全員調べだして、相続人全員の印鑑をもらわなければ所有権の移転登記ができません。もちろん、数十年経っていますので相続人も何十人となってしまっているのです。
2.遺産分割が難航した場合の税務上の注意点
上記のように一時相続の遺産分割が難航した場合でも、相続税の申告書の提出期限については通常の通り相続開始日から10ヶ月以内です。
もし、10ヶ月以内に一次相続がまとまらない場合には、 財産または債務のうち法定相続分に応じる金額を計上しなければなりません。
さらに、問題となるのは特例の適用です。
亡くなられた方の自宅などに適用できる小規模宅地等の特例や、 配偶者については一部課税しないという配偶者税額軽減は 一定の期間内に分割協議が終わっていることが適用要件となっています。
では、一次相続がまとまらなければ上記の特例はまったく適用できないのでしょうか?
答えはNoです。
一つの方法として「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する方法があります。
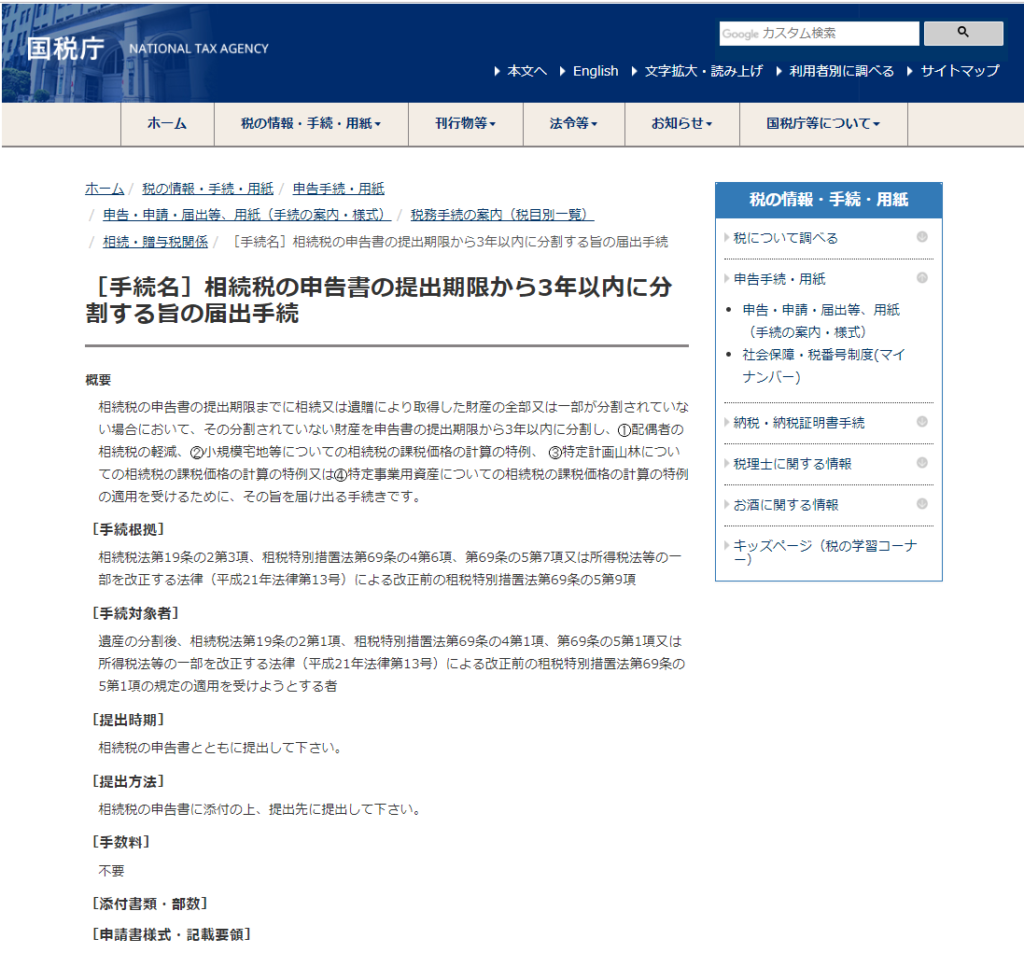
この書類を提出することにより、3年以内に分割ができれば特例を適用することができます。
ただし、この書類を出した場合であっても、一旦法定相続分の通りに相続財産を分割したものとして、さらに特例は適用しない状態で相続税を計算し、納付しなければなりません。
その後、分割ができたときには、改めて分割した内容に特例を適用して相続税を計算し、 多く納めていた相続税を返還してもらうという手続きになります。 他にも方法はいろいろとあるのですが、 詳細については税理士にご相談いただければと思います。