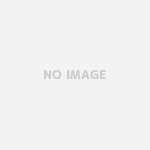「配当利回り〇〇%以上だから買い」なんて方法で株式投資している人はいないでしょうか?
しかし、現役税理士のゼンからすると配当利回りで銘柄を選ぶことにはあまり意味はないと考えています。
そこで今回は配当と株価の関係について分析してみましたのでお話しします。
1.配当利回りとは
配当利回りとは、購入した株価に対して1年間でどれだけの配当を受け取ることができるかを示す数値です。
計算式は、以下のようになります。
配当利回り(%) = 一株当たり年間配当金額 / 一株当たり株価
たとえば、年間配当100円の銘柄の株価が10,000円だったとしましょう。この銘柄を取得すると10,000円の投資額に対して1%の配当金100円が毎年もらえるわけです。
この場合、配当利回りは1%となります。
預金利息が0.02~0.2%くらいしかない今の時代ですが、株式の配当利回りはなんと平均2%前後となっています。
2.配当金の落とし穴
上のようなお話を聞くと配当ってすごく魅力的で、配当利回りが高ければ高い方が良いように思えますよね。
しかし、配当の高い銘柄には注意しなければならない落とし穴が3つあります。
①株式投資は元本保証されない
銀行の預金には元本保証がされますが、株式投資には元本保証はありません。
したがって、会社自体が万が一倒産してしまった場合、株主には1円も返せないという可能性もあり得るわけです。
②株価は変動する
銀行の預金は100万円預けたら、基本的には何年預けた後であっても元本100万円は同じ金額で返ってきます。
一方、株式投資の場合は100万円で購入したその瞬間から株価が変動します。1時間後には70万円に減っているかもしれませんし、200万円になっているかもしれません。
「配当利回り2%は魅力的!」と思って購入したのに、1日で株価が2%下落したら何の意味もありません。
③配当は会社側が自由に変更できる
銀行の預金については基本的に銀行側が勝手に金利を変更することはありません。
しかし、配当については会社側が自由に変更することが可能です。会社の業績が悪ければ当初予定していた配当金額より少なくなることもありますし、最悪の場合は配当金がなくなる(無配)の場合もあります。
配当金が少なくなったとしても株主は会社に対してなんら請求することはできませんので、結局株式を売却してその会社との縁を切ることしかできません。
3.配当は「強制利益確定」である
ゼンは配当について「強制利益確定」だと考えています。
配当金をもらうためには「権利確定日」に株式を保有している必要があるのですが、権利確定日の翌日には配当の分だけ株価が下落する「配当落ち」という現象が起きます。
つまり、株価が10,000円の銘柄で配当金が100円だった場合(配当のタイミングは年1回)、権利確定日の翌日は9,900円に下落する可能性が高いのです。
したがって、①権利確定日に株を取得し、翌日に株を売却した人も、②権利確定日の翌日に株を取得し、即日売却した人も収支は同じになります。
①株を取得 ▲10,000円 + 配当100円 + 株を売却9,900円
=収支+-0円
①株を取得 ▲9,900円 + 株を売却9,900円
=収支+-0円
もし、株式を継続的に保有していくとしても「配当落ち」という現象により、配当金額に応じた株価が強制的に利益確定されるような状態となります。
なお、株式の譲渡についての税率も配当金に対する税率も基本的には下記の通り同じですので損得はありません。
ただし、配当金については源泉分離、申告分離、総合課税の3つから選択できることにより、あえて配当金で受け取るメリットが生じる可能性があります。
【株式の譲渡・配当(源泉分離)に対する税率】
所得税・・・15% 、 復興特別所得税・・・0.315% 、 住民税・・・5%
したがって、配当利回りが高い銘柄については権利確定日において多額の配当落ちが生じることとなります。
さらに、配当利回りの高い銘柄は配当を目当てで取得している株主が多いため、万が一配当の減額が発表された場合には、株価は急降下するでしょう。
そのため、配当利回りは結局のところ株価に対しては何ら影響を与えないため、株式投資をする際には会社本来の業績などに着目した方が良いと考えます。
4.配当利回りが株価に影響する可能性
ゼンは銘柄選定にあたって配当利回りが全く役に立たないとは考えていません。配当利回りが高い銘柄を評価することもあります。
それは「下値を固くする効果」です。
ゼン自身は配当利回りに何の魅力も感じていませんが、その一方で世の中には配当利回りを気にしている投資家もいます。
そのため、配当利回りが一定以下になるとそういった「配当利回り投資家」の買い支えが入り、株価が下落しにくくなるという効果があります。
最近でいえばゼンも保有しているソフトバンク(9434)が該当します。

このソフトバンクは2018年12月19日に上場し、公募価格は1,500円でした。
しかし、初値は1,463円と公募割れし、その後も1,500円を超えることなく2019年2月15日時点で1,289円となりました。
ゼンも含め多くの個人投資家がこのソフトバンクのIPOに期待し、1,500円で株を取得したわけです。しかし、上場直後から1,500円を超えることは未だありません。
もちろん、潔く損切りした投資家もいると思いますが、含み損を抱えている「落ち武者」ならぬ「落ち投資家」が1,500円に待ち構えています。
「1,500円まで上がってきたら売る」という人が多いため、なかなか1500円は超えられない(上値が重い)状態となっています。
しかし、そんな「1,500円を超えられない呪いの銘柄」が暴落せずに1,200円台で踏みとどまっているのは、この記事のテーマである配当利回りにあるのです。
ソフトバンクは今のところ一株当たり年間75円の配当を予定しています。
ソフトバンクの顔である孫正義さんはこのソフトバンクの配当について、
「設置した電柱の減価償却があるためキャッシュフローは潤沢であり、配当性向85%は余裕」と公言しています。
年間配当が75円で株価が1,289円ですので現在の配当利回りは5.8%となります。これは日本株の中では非常に高い部類となってきます。
さらに携帯電話会社の大手であり、倒産する可能性はかなり低いですよね。
したがって、現状ソフトバンクの株価は「配当利回り投資家」が買い支えているため、なかなか株価が下がらない状態であると考えています。
反面、万が一配当が減額されるような発表があった場合には、株価が急落する可能性が高いでしょう。
配当利回りにはこのように「下値を固くする効果」があると考えています。
さらにこの効果は金利が低く、経済があまり良くないときほど効果が強くなりますので、現在のような景気にはとても有効です。
ゼンが配当利回りで評価するときは、
・株価の下落により自然と配当利回りが高くなってきた場合
・増収増益を達成しており、今後も減配される可能性は低い場合
つまり、利益を出しているのに市場から評価されず株価が下がってしまっている場合や、その評価を上げるために配当性向を上げた場合などには、配当利回りが高いことを評価します。
利益を出してもいないのに高い配当を出し続ける会社は、いずれ減配するか倒産します。そのような銘柄は配当利回りが高くても絶対に手を出してはいけません。
5.買ってはいけない高配当銘柄の末路
そんな配当利回りについて本日話題になった銘柄を紹介しましょう。
プロスペクト(3528)という銘柄があります。

プロスペクトは不動産の建築分譲や賃貸を行う会社なのですが、正直業績自体はあまり良いとは言えません。
そのため株価は2018年に入ってから右肩下がりとなっており、2019年2月14日終値は27円となりました。
そしてこの会社は一株当たり3円の配当を出す予定でしたので、配当利回りはなんと11%となっていました。
つまり、1,000株取得すると取得のために27,000円かかるけど、配当が出れば3,000円戻ってくるというわけです。
しかし、同日2月14日の引け後に「配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」が発表され、本日15日は一時17円まで下がり終値は22円となりました。
当初は一株当たり3円の配当を出す予定でしたので、少なく見積もっても3円以上は株価が下落することが予想できるわけです。
それなのに一時10円安の17円まで下落したのは配当利回り投資家たちの失望売りがあったのではないかと思います。そして、新たに業績面で評価した投資家たちが買い支えて22円まで戻したのではと考えています。
まぁ、ゼンはこの銘柄は手を出す気は全くありませんが・・・。
6.まとめ
さて、配当利回りと株価の関係について分析した結果をお話ししましたが、いかがだったでしょうか。
ゼンとしては配当利回りが高いだけで銘柄を選定することは絶対にしませんが、購入するタイミングを計るときに少し利用しています。
もともと目をつけていた割安株が値下がりしてきた際に「配当利回りからこの金額より下には下がりにくそうだな」という判断に使用しています。
皆さんも配当利回りだけに気をとられて変な銘柄に手を出さないように注意しましょう。